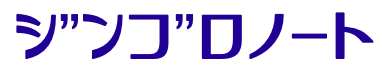こんにちは、ジンゴロ(@jingolox)です。
2024年に出版されて以来、重版をかさね、13万部越えの大ヒットとなっているという安川康介さんの「最高の勉強法」を読んでみましたので、早速、レビューしてみましょう。
本のご紹介
本日の記事で取り上げる本はこちらです。
本の概要はこちら。
脳は使い方次第! 「記憶力」× 「超効率化」× 「時短」の勉強法
13万部突破! 売れています!
414万回以上再生されているYouTubeの大人気動画「科学的根拠に基づく最高の勉強法」を 更に詳しく解説し、書籍化。
私たちが今まで慣れ親しんだ、繰り返し読む(再読)、ノートに書き写す・まとめる、ハイライトや下線を引く、 といった学習法は、実は身につきにくいやり方だった。 覚えたことを思い出す、人に教えられる=アウトプットこそが成長につながる、
研究によって検証された効率的な勉強法です。
オフィシャルサイト https://www.kadokawa.co.jp/product/322310000993/ より引用
著者は医師の安川康介さん。こちらの書籍は下記の動画を書籍化し、さらに詳しく内容を追加したものとのこと。こちらを見てから本を読んだほうが理解が早いと思います。
こんな人にオススメ
この本は以下のような方々にオススメします。
- 受験や資格試験を控えている方
- 勉強する必要があるが、十分に時間を取れない方
- 記憶や理解のメカニズムに興味のある方
著者のご紹介
この本の著者は、医師の安川康介さんです。
2007年に慶応大学医学部を卒業し、現在は、アメリカの病院で臨床医として働いているそうです。
YouTubeチャンネル「米国内科専門医 安川康介の医学チャンネル」を運営しており、登録者数は17.4万人と、結構いらっしゃいますね。
少し拝見させていただきましたが、医学的な内容の解説のみならず、一般人に興味のある話題として様々な勉強方法を取り上げているのが興味深いところです。
覚えたら寝よう!
古事記に関する論文も書いているそうです。いいですね。
安川さんは間違いなく地頭も良いのだろうと思いますが、そんな彼が最適だと思う勉強法ですから、このエッセンスを我々も少しでも取り入れ、最強の凡人を目指す、のが良いかもしれません。
科学的に効果が高くない勉強法
この本の冒頭の部分では、まず科学的に効果が高くない勉強法が列挙されています。
それは、以下のような勉強法だそうです。
- 繰り返し読む
- ノートに書き写す・まとめる
- ハイライトや下線を引く
ほうほう、マジですか。
というか、どちらかというと、これしかやっていなかったような。
「繰り返し読むことは記憶の定着に効果的」と、これまでずっと信じていました。実際、「7回読むと覚えられる」なんて話も本などでよく目にしますよね。
ところが、今回読んだ本では、こうした考えがすっかり否定されていて驚きました。詳しい理由は本書に譲りますが、ざっくり言うと、何度も同じ内容を読むうちに脳が「わかった気になる」だけで、実際にはしっかり理解できていないのだそうです。
「わかった気になる」と「本当にわかる」の違いって、確かに奥が深いですよね。それに加えて、再読する場合には「どれくらい間隔をあけるか」がとても重要なのだそうです。
私にとって、ノートに書き写す・まとめる行為は勉強の手法としてはしばしば取り入れていました。この方法がなぜ好きかというと、きっと、アウトプットとして目で見て成果が残るからなんですよね。。。
結局のところ、有効な学習をするためには「繰り返し読むこともしない、まとめも作らない」という考え方に行きつくようですが、これまでの勉強の仕方を全否定されている方も多いのではないでしょうか。ぜひ本書を読んでみて、自分自身の勉強法を見直すべきか否か、確かめてみてください。
科学的に効果が高い勉強法
次の章では、以下の通り、4つの科学的に効果が高い勉強法が紹介されています。
- アクティブリコール
- 分散学習
- 精緻的質問と自己説明
- インターリービング
実践するだけで勉強の効率は劇的にかわってくるそうです。
アクティブリコールとは、簡単にいうと、覚えたことを脳の外部に引き出す(思い出す)ことを言います。
また、その方法としては、単純に問題集を解く、ということではなく、例えば、白紙に自分の覚えたことをつぶやきながら書きだすといった方法が紹介されています。
これって、結構ストイックな作業ですよね。脳にかかる負担はかなり高そうです。
アウトプットすることで、記憶の定着を計ることによって勉強の効率を高めることは有用なことは体感的には理解していますが、実際やるのは結構大変なこともあってなかなか後回しになってしまいがちですよね。
実際に、アクティブリコールを勉強のプロセスにしっかりと組み込むことが大事だと思いますが、それを計画的にやりこなすための記憶力と学習に対する意志の強さが必要かと思います。
インターリービングと言うのも聞きなれない言葉でしたが、一言でいえば、異なった複数のトピックや分野を交互に(まぜこぜに)学習する、という方法です。
この方法は数学の学習に特に向いている方法とのことですが、数学以外にも他の分野の学習においても効果が示されているということで、是非意識的に取り組んでみたい方法だと思いました。
本書ではこれらの勉強法以外にも、睡眠や運動、カフェイン摂取のことなど、勉強の効率を上げるために必要な様々なトピックについて説明されていますので、勉強に役立つ幅広い知識を得ることができます。実践的な内容が多く、勉強をより効果的に進めたい人におすすめの一冊です。
最後に
世の中には、星の数ほどの「勉強法」が存在していると思います。
おそらく、万人にとっての最適な勉強法というものは存在せず、各個人の性格や能力、置かれている環境などによって、最適な勉強法は異なるものでしょう。
今回ご紹介した「最高の勉強法」も、そうした数ある方法のひとつといえますが、勉強法を模索されている方にとっては、試してみる価値のあるアプローチだと思います。
そもそも、私が思うに、自分にとって本当に最適な勉強法は、本気で勉強に取り組んだときにしか見えてこないものです。
越えられない壁の存在は、それを越えようとする者にしか見えませんし、その壁の越え方も、挑戦した者にしか分からないものです。本気で取り組み続け、試行錯誤を重ねた先に、ようやく自分にとっての「最適な勉強法」が見えてくるのだと思います。
少々まとまりのない締めになってしまいましたが、皆さんの「勉強」という果てしなき旅の成功を心より願っています。
それでは、また。