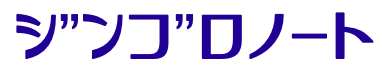こんにちは、ジンゴロ(@jingolox)です。
仕事でもプライベートでも、絶えず発生するタスクをどう管理するかについて、多くの方が悩み、方法を模索されているのではないでしょうか。
「タスク処理能力 = タスク管理力 = (人としての)キャパシティ」という等式は、多くの場面で成り立つのではないかと考えています。
今回のブログでは、サラリーマンを20年以上務めてきた私ジンゴロが思う「タスク管理」について、少し語ってみたいと思います。
タスク管理に王道はない
タスク管理術は、単なる方法論を超えて、一種の哲学として語られることも多いですよね。
代表的な手法としては、デビット・アレン氏が提唱する「Getting Things Done(GTD)」が有名です。2001年の出版以来、世界中で翻訳され、多くのフォロワーを生み出してきました。ちなみに、今月には最新の改訂版がリリースされています。
このGTDをもっともシンプルに説明すると、頭の中にあるタスクをすべて書き出し、整理・分類することで、記憶の負荷をなくし、次にやるべきことに集中するというものです。
理屈としては素晴らしいのですが、管理が高度化する一方で、ちょっとしたマイナス面もあるのでは…というのが私の正直な感想です。
まず、GTDをスムーズに実践できるようになるまでに数年かかると言われています。「たかがタスク管理、されどタスク管理」。多くの場合、私たちの目的はタスク管理のプロフェッショナルになることではありません。なるべく時間はかけたくないのが本音です。
また、GTDの肝として「週次のメンテナンス時間」を確保することが提唱されていますが、目が回るほど忙しい時期に、果たしてその時間を取れるのか…という問題が常について回ります。
デジタル化の進展で、情報は書類 → メール・SNS、書類 → PC・スマホとどんどん複雑化し、アナログ情報とデジタル情報がカオス状態になりつつある今、タスクを常に最新状態で維持するだけでも大変です。
メンテナンスされていないタスク管理表は、途端に「心の負債」として重くのしかかり、ファイルを開くのもおっくうになります。
つまり、丁寧に自分のタスクと向き合い、確実にこなしていく少しの時間的余裕、そして几帳面さが必要なタスク管理術なのです。はまれば効果は絶大ですが、人によっては心理的負荷が高まる可能性もあると思います。

タスク流入経路を把握する
先ほどのGTDにおける「頭の中からすべて書き出す」アプローチは、多くの働く人にとって重要です。もちろん、そもそもそんなことをしなくて済むなら最高ですが…それはリタイア後のお気楽な生活として実現できると思うので、それまで取っておきましょう。
脳のメモリ量が莫大でない限り、タスクをすべて可視化するのは大事ですし、そのアクションだけでも自分流の管理方法を確立すべきだと思います。その状態が維持できていれば、すでに立派なタスク管理です。
私が考える、タスク管理においてもっとも重要なポイントは「タスクの流入経路をすべて把握し、漏れをなくすこと」です。
自分の場合のタスク流入パターンをリストアップして、管理リストへの組み込みやすさを4段階で整理してみました。
難易度1:メールによる依頼
他人や会社からのメールで、きれいな形でタスクとして発生するものは比較的管理しやすいです。ただ、1日のメール数が100を超えるような場合はオーバーフローして、漏れが出てしまうかもしれません。
難易度2:上司・同僚からの対面や電話での依頼
依頼内容が記憶に残りやすいので管理しやすいですが、内容や締め切りが不明瞭な場合も多いです。確認不足のまま進めると、後々大問題になることもあるので、難易度2としました。
難易度3:TeamsなどのSNSツールからの依頼
SNSツール上では、スレッドの洪水の中にタスク依頼が流されがちです。送信者もメールで送ったかSNSで送ったか混乱することもあり、まさにタスク管理の鬼門です。皮肉ですが、コミュニケーションツールとして優秀なSNSがタスク管理を難しくしています。
難易度4:会議中の会話から発生するタスク
会議ツールが発達した今、一日中会議という方も多いのでは?
私が一番管理が難しいと感じるのは、この会議中の「会話の中から発生するタスク」です。
例:
上司「〇〇確認して、△△までに送っておいてくれる?」
自分「わかりました。やっておきます」
議事録が残らない会議も多く、その場で記録に残さないとすぐに消え去るタスクです。しかも些細な依頼内容が多いので、記憶にも残りにくい…。でも、こういうタスクがプロジェクトに大きな遅れをもたらすこともあります。
最近ではAIで議事録を作成するケースも増えていますが、100%の精度ではないので、やはり自分で記録するしかありません。
会議が一日に5~6本連続していると、タスクが絶えず発生し続ける中で、どうやって実施漏れを防ぐかが重要です。
「依頼内容をメールで送ってくれますか?」と頼める”強い人”になるのが一つの解決策かもしれませんが、そう簡単にはいかないですよね(笑)
自分なりのタスク管理を確立せよ
タスクの流入経路をすべて押さえたら、それぞれどう管理・記録していくかを決めなければいけません。
経路ごとに管理方法を変えるかどうかに決まりはありません。理想は一元化ですが、正直、あまり労力はかけたくないものです。
私のタスク管理における最優先事項は、もう圧倒的に「タスクを見逃さない・失念しないこと」です。本記事では詳細について言及しませんが、私は結局デジタル→アナログに戻り、付箋を使ったタスク管理をしています。
「え、結局ポストイット!?」と思われるかもしれませんが、これが一番漏れが少なく、タスクが発生した瞬間にサッとチケット化できるのが強みです。
忙しくなればなるほど、デジタルツールに入力する時間さえ惜しいですから。
特に、私にとっては、会議中に突発的に発生する多数のタスクを取りこぼさないようにすることが重要で、発生した直後にポストイットにさっと書くことで、タスクを漏らすことは無くなります。
そのあとに、ポストイットから他の管理ツールに書き写すといったこともしません。多分、それをプロセスに入れた瞬間に、タスク管理が破綻することが目に見えていますので(笑)
最後に
今月「はじめてのGTD ストレスフリーの整理術」が新装版として出版されたこともあり、あらためて自分のタスク管理について振り返る機会となりました。
これを機に、皆さんも「自分に合ったタスク管理の形」を再考してみてはいかがでしょう。
あなたの働き方や生活をより快適かつクリエイティブ化するヒントが何か見つかるかもしれません。
それでは、また。